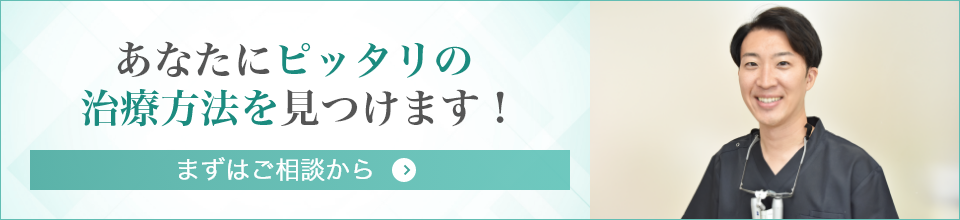Column
「インプラント周囲炎」の症状・特徴とは?原因や治療方法をチェック

インプラント治療で使用される歯根や歯は人工物のため、虫歯になったり痛みを感じたりすることはありません。
ただし、治療後のケアを怠ると“インプラント周囲炎”を発症して、口腔機能に悪影響を及ぼすおそれがあります。
そこで本記事では、インプラント治療後に注意が必要なインプラント周囲炎について、その原因や治療方法、予防方法を含めて解説します。
治療後も良好な口内環境を維持するために、参考にしてみてください。
横浜で明瞭な料金体系のインプラント治療をお探しの方は「あきもと歯科」へご相談ください
インプラント周囲炎とは?
本題に入る前に、インプラントの構造について改めて確認しておきましょう。
インプラントは、基本的に以下の3つのパーツで構成されています。
インプラントの基本構造
- インプラント体:顎の骨に埋め込まれる人工歯根
- アバットメント:インプラント体と人工歯を連結するための支台部
- 人工歯:天然歯に相当する上部構造
上記のインプラント体を固定している顎の骨や歯茎が歯周病菌に感染し、炎症を引き起こす細菌感染症のことをインプラント周囲炎といいます。
天然歯における歯周病に相当する疾患と捉えると、理解しやすいかもしれません。
インプラント周囲炎は、天然歯に発症する一般的な歯周病と比べて症状の進行が速いことが特徴です。
天然歯の場合、歯と顎の骨のあいだに“歯根膜”とよばれる薄い膜があり、その歯根膜が歯周病の進行を抑える役割を担っています。
しかし、インプラント治療で埋入する人工歯根には歯根膜がなく、治療後は細菌に対する抵抗力が弱くなります。
そのため、いったん歯周病菌に感染すると、炎症や骨の分解が急速に進行してしまうのです。
このように症状の進行が速いことから、インプラント周囲炎は気づいたときには重症化しているケースもあります。
インプラント治療を受けた箇所に少しでも違和感がある場合は、早急に歯科医院を受診することが重要です。
インプラント周囲炎の症状
インプラント周囲炎の症状は、段階的に進行していきます。
初期には“インプラント周囲粘膜炎”が認められ、やがてインプラント周囲炎へと移行し、徐々に症状が悪化します。
初期段階であるインプラント周囲粘膜炎では、歯茎の腫れや出血といった症状が現れるのが一般的です。
しかし痛みがほとんどなく、発症に気づかないことも珍しくありません。
インプラント周囲粘膜炎の自覚がないまま症状が進行した場合、炎症が顎の骨にまで広がり、インプラント周囲炎の状態に至ります。
この段階になると、歯茎からの出血にくわえて膿が出始めるようになり、顎の骨も少しずつ分解され、次第に失われていきます。
さらに骨の分解が進むと、インプラント体が不安定となって最終的に脱落してしまうのです。
インプラント周囲炎になる原因
一般的な歯周病と比べて症状の進行が速く、発症に気づきにくいインプラント周囲炎ですが、原因をあらかじめ把握しておくと予防や早期発見につながります。
この項では、以下に挙げるインプラント周囲炎を発症する原因について具体的に解説します。
インプラント周囲炎になる原因
- セルフケアを怠っている
- 喫煙している
- 歯周病の治療が不十分なままインプラント治療を受けた
- 糖尿病に罹患している
- 貧血である
- 歯ぎしりや食いしばりの癖がある
セルフケアを怠っている
毎日の歯磨きをはじめとするセルフケアを怠ると口内環境が不衛生になり、インプラント周囲炎の原因である歯周病菌が増殖するおそれがあります。
セルフケアを実践して歯周病菌の増殖を食い止めることで、インプラント周囲炎の予防に期待できます。
インプラント治療後は、歯科医院で定期健診を受けることはもちろん、日常生活のなかでご自身によるケアも忘れずに行いましょう。
喫煙している
喫煙による血行の悪化も、インプラント周囲炎を発症する原因の一つと考えられています。
たばこに含まれるニコチンや一酸化炭素には血管を収縮する作用があり、血液循環に支障をきたすため、歯茎の健康にとって非常に有害です。
具体的には、血流の悪化によって歯茎に必要な栄養素や酸素が行き届かなくなり、感染症や炎症への抵抗力が弱くなります。
インプラント治療後の顎の骨や歯茎は、特に細菌に感染しやすくなっているため、この状態で喫煙を続けるとインプラント周囲炎の発症リスクがさらに高まります。
歯周病の治療が不十分なままインプラント治療を受けた
歯周病の治療を終える前にインプラント治療を受けると、インプラント周囲炎につながる可能性があります。
これは、口内に残っている歯周病菌がインプラント埋入後に炎症を引き起こすためです。
インプラント周囲炎の発症を防ぐには、治療を受ける前に歯周病を完治させておくことが大切です。
糖尿病に罹患している
無関係のようにも思えますが、糖尿病もインプラント周囲炎を引き起こす原因の一つです。
糖尿病を患っている方は、高血糖が続くことで免疫力が低下し、感染症への抵抗力が弱まる傾向にあります。
これは歯周病菌に対しても同様であるため、糖尿病を患っている方はインプラント周囲炎を発症するリスクが高いとされています。
貧血である
貧血は、体内の酸素を運ぶ赤血球やヘモグロビンが不足している状態です。
酸素の供給が十分でないと、歯ぐきを含む全身の組織が酸素不足となり、免疫力が低下します。
細菌感染への抵抗力が弱まることで、インプラント周囲炎を悪化させるおそれがあります。
貧血の症状がある場合は、歯ぐきの血流が悪く炎症の治りが遅れる傾向があるため、注意が必要です。
インプラント治療を受ける前に貧血の有無を確認し、必要に応じて食事やサプリメントなどで鉄分を補う必要があります。
歯ぎしりや食いしばりの癖がある
無意識に歯を強く噛みしめる癖がある場合も、インプラント周囲炎を誘発してしまうかもしれません。
このような強い噛みしめは、インプラント体や周囲の歯茎に大きな負荷をかけるため、インプラントのまわりの組織が損傷して歯周病菌に感染する可能性があります。
インプラント周囲炎は放置したらどうなる?
インプラントの周囲には、天然歯のような歯根膜が存在しません。そのため、炎症が起きると直接骨に影響しやすい構造です。
炎症が続くと、免疫細胞が炎症性物質を放出し、破骨細胞が活性化してインプラントを支える骨が徐々に溶けていきます。
初期は痛みが少なく気づきにくいものの、進行すると膿や口臭などの自覚症状が現れます。
症状が悪化するとインプラント自体がぐらつき、脱落するおそれもあります。
インプラントが脱落した場合は、失った骨の再生から治療を始める必要があります。
骨の再生には時間・費用がかかるため、早期発見・早期治療が重要です。
インプラント周囲炎の治療方法
万が一、インプラント治療後に炎症が起こってしまった場合に備えて、実際に行われる治療法も把握しておきましょう。
主に“非外科的治療”と“外科的治療”の2種類があるため、以下で詳しく解説します。
非外科的治療
非外科的治療とは、歯茎を切開せずに回復を促す治療方法のことです。
具体的な治療方法は、以下の通りです。
非外科的治療の方法
- 歯周ポケット内の洗浄と薬剤の注入
- 周囲の歯石除去
- 抗生物質の投与
- 歯磨きなどの生活指導
上記のように、歯周ポケット内の歯垢や細菌、また周囲の歯石を除去して、インプラント周囲炎による炎症を抑えていきます。
また、炎症反応が強い場合には、抗生物質を投与して症状を和らげることもあります。
なお、歯科医院によっては正しい歯磨きの仕方や生活習慣の改善方法についてアドバイスしてくれるため、治療後もご自身で適切なケアを実施できるでしょう。
外科的治療
外科的治療では、歯茎を切開してインプラント体を露出させたうえで、表面の清掃や殺菌を施し、あわせて周囲に付着した歯垢や細菌を除去します。
また、炎症がひどい場合には該当部位を取り除くこともあるでしょう。
なお、顎の骨に固定されたインプラント体が不安定になるほど炎症が進んでいる場合は、インプラント体を抜き取ることもあります。
その際、顎の骨が十分に残っていれば再度インプラント体を埋入できますが、骨の量が足りないのであれば骨移植が必要となります。
再生療法
再生療法は、炎症や感染した組織を除去し、人工骨や骨補填材、再生膜などを用いて自然な骨の再生を促す治療法です。
近年では、PDGFやBMPといった成長因子を用い、治癒を促進する治療法も行われています。
再生療法により、骨の吸収が進んだ場合でも骨量を回復させ、インプラントを残せる可能性を高められます。
インプラント周囲炎を予防する方法
最後に、インプラント周囲炎の予防方法を詳しく紹介します。
セルフケアを徹底する
インプラント周囲炎を予防するために最も重要なのは、毎日のセルフケアを継続することです。特別なケアは不要ですが、正しいブラッシングを続けることが欠かせません。
人工歯の表面だけでなく、歯と歯のあいだや奥歯まで意識して磨くようにしましょう。
歯間ブラシやタフトブラシを併用すると、通常のブラッシングでは落としにくい汚れを効果的に除去できます。
粒子の細かい歯磨き粉を使うと、インプラントや歯ぐきを傷つけずに歯垢が落とせます。
人工歯の根元部分はくびれて汚れが溜まりやすいため、丁寧なケアが必要です。
ブラッシングに不安がある場合は、かかりつけの歯科医院で正しい磨き方の指導を受けることをおすすめします。
セルフケアを徹底する
喫煙は歯ぐきの血流を悪化させて免疫力を低下させるため、炎症が起こると治りにくくなります。 節煙や禁煙を心がけ、最終的に断煙を目指すことも、予防に有効な手段のひとつです。
生活習慣を見直すとともに、糖尿病などの全身疾患を治療することも、インプラントを長期的に維持するために欠かせません。
定期的にメンテナンスを受ける
インプラント治療後は、歯科医院でメンテナンスを定期的に受けることで、インプラント周囲炎の予防につながります。
ご自身でのセルフケアにくわえ、定期的に通院し、インプラント体のネジの緩みや噛み合わせなどを確認してもらいましょう。
その際、炎症の有無を確認してもらうほか、普段のブラッシングでは落としきれない汚れを除去してもらうことで、口内環境を清潔に保てます。
インプラント周囲炎は歯周病に相当する細菌感染症の一種
今回は、インプラント周囲炎について、発症する原因や治療方法、予防方法をお伝えしました。
インプラント周囲炎とは、インプラント治療後の顎の骨や歯茎が歯周病菌に感染し、炎症を起こしている状態のことを指します。
初期段階では自覚発症に気づけない場合があるため、治療後はセルフケアや定期健診で予防に徹することが大切です。
横浜エリアにお住いで、インプラント治療後に気になる症状がある方は、あきもと歯科にご相談ください。
一人ひとりの口腔状態に応じて、最適な治療法をご提案いたします。
インプラントについてのご相談はこちら